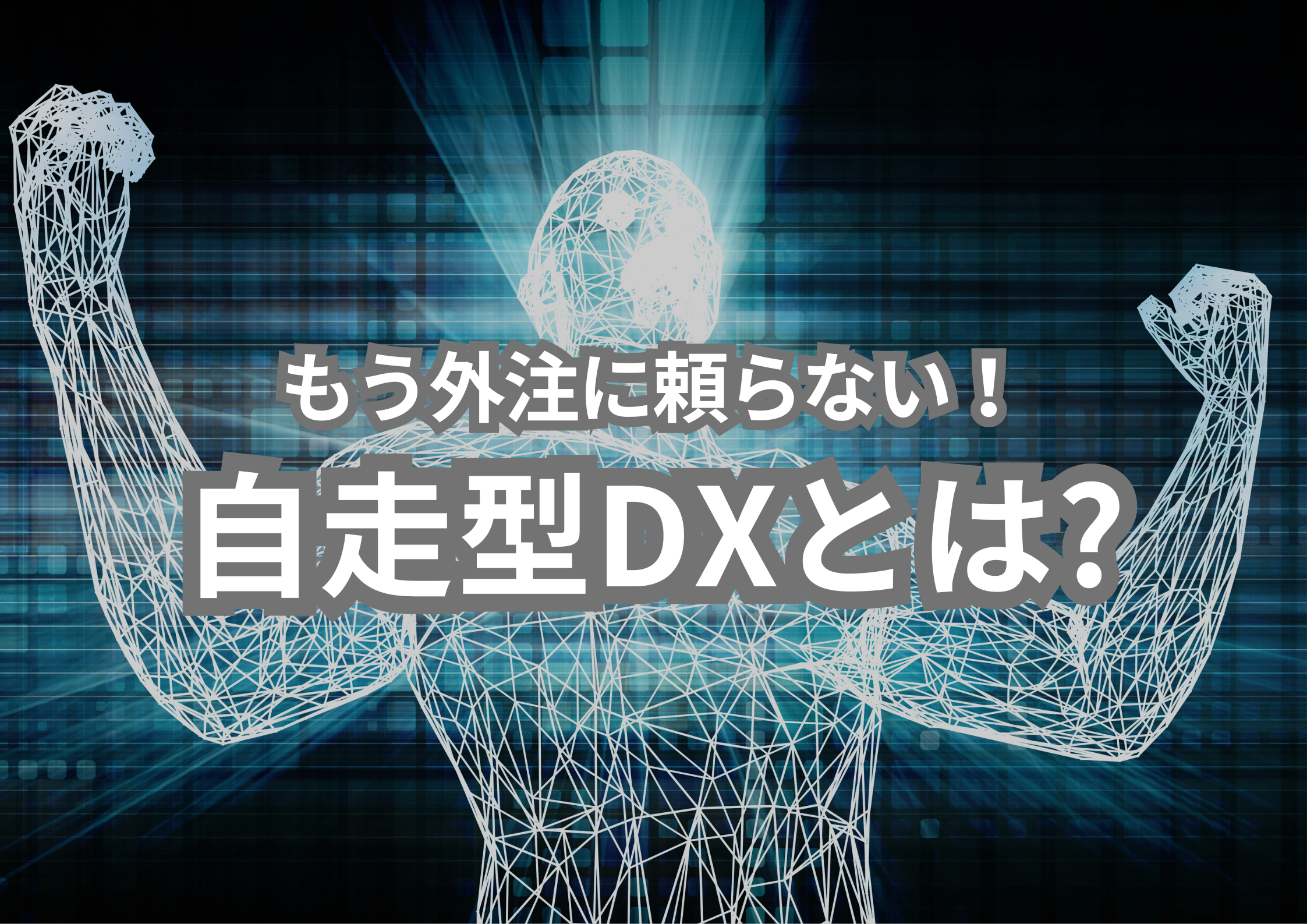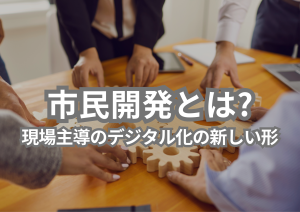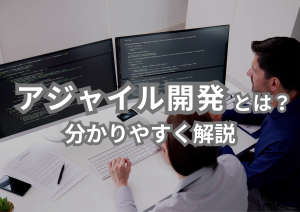多くの企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組む中で、「システムを導入したけれど、現場で使われていない」「ベンダーに任せたものの、社内にノウハウが残らない」といった声を耳にする機会が増えています。
特に中小企業では、限られた人材と予算の中で、こうした“形だけのデジタル化”に悩まされているケースが少なくありません。
なぜこのようなことが起きるのでしょうか。それは、DXの取り組みを“外注任せ”にしている限り、社内に主体性や改善力が育ちにくいからです。
そこで注目されているのが、“自走型DX”を支援する「伴走支援」というアプローチです。
自走型DXとは -ツールではなく、“変化に対応する力”を育てること
DXという言葉から、多くの方は「最新のITツールの導入」や「紙業務のデジタル化」といった技術的なイメージを持たれがちです。しかし、ツールを導入しただけでは、それが本当に価値を生むとは限りません。むしろ、現場で“使いこなせないまま放置される”ケースが後を絶ちません。
こうした失敗の多くは、「現場が主体になっていない」ことが原因です。
自走型DXとは、現場の業務担当者が自らの手で業務を見直し、必要なツールや仕組みを選び、改善を積み重ねていくスタイルです。もちろん、全員がITの専門家である必要はありません。小さな改善を“自分たちで”繰り返せる力を育てることが、持続可能なDXへの第一歩なのです。
たとえば、紙で運用していた申請フローをGoogleフォームに置き換えたり、毎日手作業していた集計業務をスプレッドシートで自動化したりといった“小さなデジタル化”も、自走型DXの一つです。
こうした積み重ねによって、現場は少しずつ“自分たちで変えられる”という自信をつけていきます。
伴走支援とは -“できるようになる”まで一緒に進む支援
従来のIT支援といえば、「要件をヒアリングして、完成品を納品する」スタイルが主流でした。しかしこのアプローチでは、完成後の運用や改善が現場任せになってしまい、結局は使われなくなるリスクがあります。
そこで注目されているのが「伴走支援」という支援スタイルです。
これは、単に“何かを作る”のではなく、現場とともに課題を整理し、ツールの使い方や改善方法を学びながら、継続的に支援していくアプローチです。
伴走支援の本質は、「導入」ではなく「内製化支援」にあります。つまり、「他人にやってもらう」から「自分たちでできるようになる」までを支援すること。自走型DXを実現するには、この“育てる支援”が欠かせません。
なぜ今、伴走支援が求められているのか?
近年、企業を取り巻く環境は大きく変化しています。少子高齢化による人材不足、IT人材の確保難、サプライチェーンや働き方の多様化など、中小企業にとっては特に厳しい状況です。
こうした中で、外部にすべてを委ねるスタイルでは変化への対応が遅れ、コストもかさみ、継続性も危うくなります。一方で、現場が自ら改善に取り組める「自走力」を身につけていれば、ツールや体制の変更にも柔軟に対応できます。
このような背景から、単なる導入支援ではなく「共に考え、共に成長する」伴走支援のニーズが高まっているのです。
外注ではなく“内から動ける力”を育てる
DXとは、本来「業務の在り方を変える」ことに本質があります。それを持続可能なものにするには、「変化に強い組織づくり」が不可欠です。
そのためには、現場が改善を回し続けられる“自走力”を育てることが、最も重要な投資ともいえるでしょう。
伴走支援は、そうした変化を一緒に伴いながら実現していく新しい支援の形です。特別なITスキルがなくても、小さな改善から始めて、自社内に改善サイクルを根付かせる。それこそが、本当の意味での「自走型DX」といえるでしょう。
企業の課題をDXで解決します
「DXを始めたいけど、どこから手を付けたらよいか分からない…」
「自社システムは自社で管理したい…」
「製造ラインを効率化したい…」
DX推進や社内のデジタル化にお悩みを抱えていませんか?
株式会社ウイングでは、経営者、管理部門、現場、システム部門など、幅広いお客様のニーズに合わせて最適なソリューションをご提案します。
ウイングが提供するソリューションの詳細は、以下のサイトからご覧ください。