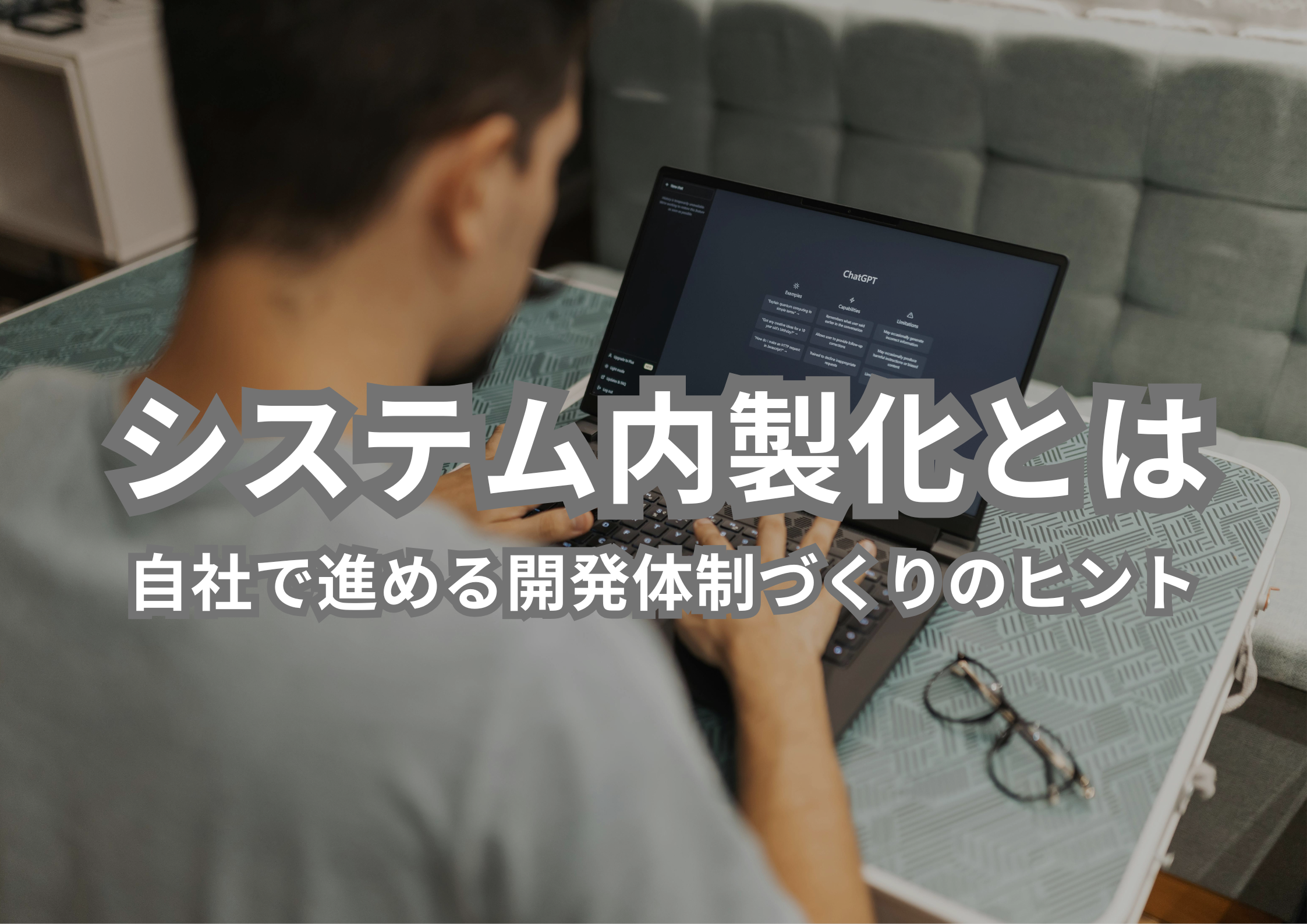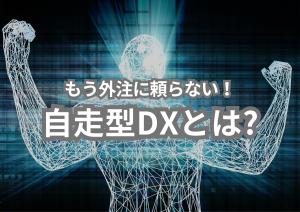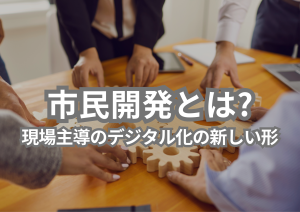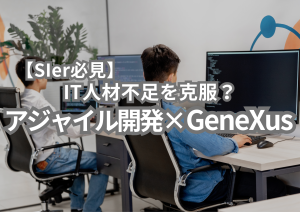「内製化」とは?
「内製化(ないせいか)」とは、自社の業務に必要なシステムやツールを、自社内でつくることを意味します。
これまで多くの企業では、システム開発を外部のIT企業(=ベンダー)に依頼していました。たとえば、業務アプリを作りたいとき、ITベンダーに仕様を伝え、開発から運用までをすべて“丸投げ”するのが一般的でした。
しかし、今ではそのスタイルが変わってきています。
内製化=「自社でつくる」「自分たちで育てる」
内製化とは、「システムをつくる力」や「改善する力」を社内に持つことです。すべての社員がプログラミングできる必要はありませんが、以下のような姿を目指すのが内製化です。
- 業務部門が自分たちで使いやすいシステムをつくる
- 情報システム部門が現場と連携しながらすばやく改修する
- 小さな改善を継続的に実施して、業務のムダをなくしていく
最近では、「ローコード」や「ノーコード」といった、プログラムを書かずにアプリを開発できるツールが広まり、現場主導の内製化も現実的になっています。

なぜ今「内製化」が注目されているのか?
DX(デジタルトランスフォーメーション)が企業の競争力を左右する中、業務システムのあり方が見直されています。これまでは外部ベンダーに開発を依頼するのが主流でしたが、今、多くの企業が「内製化」を模索し始めています。
その背景には、以下のような市場動向や構造的課題があります。
DX推進と「スピード重視」の経営戦略
経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」では、レガシーシステムの維持により企業の競争力が低下する「2025年の崖」という警鐘が鳴らされました。以降、民間企業はDX(デジタルトランスフォーメーション)の加速を迫られるようになります。
DXの本質は単なるIT導入ではなく、変化に柔軟に対応できる組織づくりと業務変革です。これを支えるには、外部ベンダーに依存するのではなく、「自社で迅速に対応できる開発体制」が不可欠になってきています。
出典:経済産業省「DXレポート」(2018年)
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_report.html
外注開発の限界とコスト構造の問題
これまで多くの企業では、システム開発をSIerに外注する「請負開発」が主流でしたが、以下のような問題が浮き彫りになっています。
- 要件定義〜リリースまで半年~1年以上かかる
- 小さな改修にも稟議・発注が必要で、改善が遅れる
- 人月単価の高騰・人材不足によるコスト増加
特に中堅・中小企業では、スピードと柔軟性に欠ける外注モデルでは競争優位を築けない状況が広がっています。
変化に即応できる「アジャイル体制」の必要性
今日のビジネス環境では、市場変化や顧客ニーズに即応する能力が不可欠です。そうした中で注目されているのが、開発と業務部門が密接に連携し、短期間で繰り返し改善するアジャイル開発体制です。
アジャイル開発(=短期間で継続的に機能をリリースしながら改善)は、業務部門との密接な連携が求められるスタイルです。
しかし、従来型の請負開発では、要件確定〜納品までが「一括契約」であるため、アジャイルに動くのは困難です。そのため、社内に開発能力を持ち、業務と直結した改善が行える内製化の重要性が増しています。
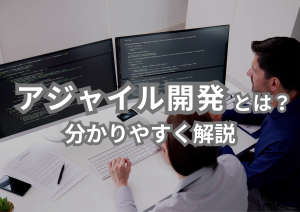
IT人材不足と“スキルの内製”への転換
経済産業省の調査によれば、2030年には最大79万人のIT人材が不足すると試算されています(「IT人材需給に関する調査」2020年版)。
企業は「外から人を調達する」だけではなく、自社内にITスキルを育成・蓄積することが、競争力維持のカギとなります。
その結果、「技術は外部任せ」だった体制から、ITスキルやノウハウを内製化する流れが生まれているのです。
※出典:経済産業省「IT人材需給に関する調査」(2020年)
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/houkokusho.pdf
ローコード・ノーコードの普及により、誰でも始められる環境が整備された
内製化を後押しする技術的背景として、ローコード/ノーコードツールの普及があります。
かつてはシステム開発と言えば、専門的なプログラミングスキルが不可欠でしたが、プログラミング経験がなくても、ドラッグ&ドロップや画面操作だけで業務アプリを構築できるツールが登場し、非エンジニアでも開発に携われるようになりました。
たとえば、GeneXusのような自動生成型ローコードツールを使えば、現場の業務担当者がアプリケーション開発に参加できます。
これにより、現場主導での業務改善やアプリ開発が可能となり、内製化のハードルが劇的に下がっています。
内製化がもたらす3つのメリット
では、実際に「内製化」を進めることで、企業にはどのような変化がもたらされるのでしょうか?
ここでは、実務的にもインパクトが大きい3つの主要なメリットを取り上げます。
1. 業務変化に素早く対応できる
外注開発では「要件定義 → 見積もり → 稟議 → 発注 → 開発 → テスト → 納品」という長いプロセスを経る必要があり、たとえ小さな変更でも数週間~数ヶ月かかるのが一般的です。
一方、内製化により社内で開発・改修が可能になると、こうしたリードタイムが大幅に短縮されます。
「現場の課題を、現場がその場で直す」ことができるため、業務の変化や市場ニーズへの即応が可能になります。
たとえば、ある製造業の中堅企業では、社内でローコードツールを活用し、月に3~5本の業務アプリを自作して改善を回す体制を実現しています。外注していた時代と比べて改善スピードが5倍以上になったという事例もあります。
こうした俊敏な対応力は、顧客満足度や収益性の向上にも直結します。
2. 業務ノウハウの見える化・共有
業務改善やシステム開発を外注に任せてしまうと、「なぜその設計にしたのか」「業務の前提や背景は何か」が属人化・ブラックボックス化しがちです。
しかし、現場担当者が開発プロセスに主体的に関与することで、業務フローやルール、判断基準といった**“現場の暗黙知”が構造化され、可視化されます**。これにより、以下のような効果が期待できます:
- 業務フローの標準化とプロセスの洗練
- 教育・引き継ぎが容易に(新入社員・異動者も早期にキャッチアップ可能)
- 属人化していた作業のリスク低減と継続性向上
さらに、システムの画面設計や業務ロジックの形でノウハウを形式知化することは、企業の資産価値を高めることにもつながります。
3. 中長期的にコスト効率が良くなる
内製化には「自社で開発環境を整える」「社員を育成する」といった初期コストがかかるのは事実です。
しかし長期的に見れば、以下のような外注コストの構造的な問題を解消できる可能性があります:
- 人月単価の高騰(特にDX領域では月100万超も珍しくない)
- 改修1件ごとの見積・契約コスト
- 不透明なマージン構造(元請→下請→孫請)による中間コストの増大
実際にIPA(独立行政法人情報処理推進機構)が2023年に発表した調査でも、システム開発費のうち平均30%以上が中間マージンで占められているという分析があります。
また、内製化によって保守・運用も自社で対応できるようになれば、継続的な外注契約やベンダーロックインからの解放にもつながります。
結果として、トータルでのTCO(総所有コスト)を大幅に抑制しながら、継続的に業務改善を進められる体制が整うのです。
※出典:IPA「IT人材白書2023」
https://www.ipa.go.jp/jinzai/jigyou/about.html
失敗しない!内製化スタートアップの5ステップ
とはいえ、「いきなりすべてを内製化」は現実的ではありません。段階的に、着実に始めることが成功のカギ。以下に、失敗しない進め方のヒントを5つご紹介します。
① 現状把握と小さな業務の棚卸しから
まずは自社の業務とシステムを可視化し、「どの業務が手作業で非効率か」「何を内製できそうか」を整理しましょう。最初から全社システムを内製する必要はありません。Excel管理の申請業務や、紙ベースのチェックフローなど、小規模な業務改善から始めるのが現実的です。
② IT人材がいなくても始められる「ローコード・ノーコード」の活用
「うちはエンジニアがいないから…」という声もありますが、最近ではローコード開発ツールを使えば、非エンジニアでもアプリ開発が可能です。ITと現場が協力しながら、少しずつ“自社で作る力”を養うことができます。
③ 社内に“理解者”を育てる(スモールチームをつくる)
最初は全社的な取り組みでなくても構いません。小さな部署、意欲のある担当者、業務理解のあるメンバーで「内製化チーム」をつくり、社内実績を積むことから始めましょう。
④ 外部パートナーを“伴走型”で活用する
すべてを自社だけで行う必要はありません。重要なのは、「開発を丸投げする外注」ではなく、一緒に設計し、手を動かし、内製化のノウハウを得られるパートナーを選ぶこと。最初は手取り足取りでも、徐々に自立していけば良いのです。
⑤ 成功体験を社内で共有する
最初に改善できた業務や成果を、社内報・朝会・部内MTGなどで共有しましょう。「うちの業務でもできるかも」と、他部門の巻き込みにつながります。成功体験は、社内の内製化文化を醸成する第一歩です。
実際に取り組んだ企業の事例をご紹介
例えば、ノバレーゼ様は、老朽化した旧システムからの移行にGeneXusを活用。現場の声を反映したUI設計で、ユーザー満足度の高いシステムを開発しました。今では開発も内製化し、継続的な改善を進めています。
他にも、鈴廣蒲鉾本店様では、全社的なDX推進にGeneXusを導入。現場部門と情報システム部が連携し、自社開発体制を構築することで、柔軟かつスピーディーなシステム運用を実現しています。
【無料DL】内製化・業務改善のヒントが詰まった事例集はこちら!
「ウチでもできるかも」そう思った方へ。
ローコード開発ツールGeneXusを活用して、システム内製化・DXに成功した企業の事例をまとめました。
▶ \ 今すぐダウンロード /
【無料】内製化・DX成功企業の事例集(PDF)
事例集をダウンロードする
内製化は「小さく始めて、大きく育てる」
システムの内製化は、決して一朝一夕に実現できるものではありません。しかし、ポイントを押さえて小さく始めれば、着実に成果が出ます。
「外注 vs 内製」という二択ではなく、自社の業務を深く理解し、外部とうまく協力しながら“自走力”を育てる。それが、これからのシステム開発の新しいスタンダードです。